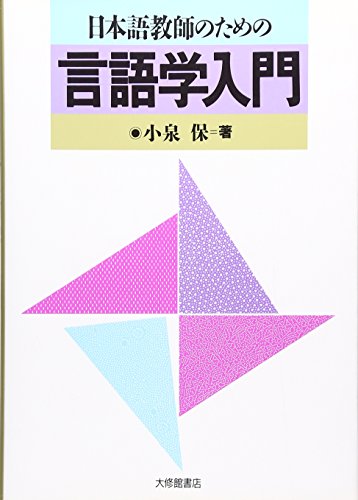対格言語と能格言語
言語のタイプの分類に、対格言語と能格言語がある。
対格言語とは、「主語」である主格に対し他動詞の「目的語」が対格となって区別されるものをいう。
つまり、
太郎が(主格)次郎を(対格)殴る(他動詞)。
次郎が(主格)走る(自動詞)。
のような形式が対格言語である。
一方、能格言語とは、他動詞の「目的語」と自動詞の「主語」がともに「絶対格」という一つの格で表され、他動詞の「主語」を表す格は「能格」という格で表されるものをいう。
つまり、仮に語順をSOVとすると、
S(能格) O(絶対格) V(他動詞)
S(絶対格) V(自動詞)
のような形式になる。
能格言語は一見奇妙な感じがするかもしれない。
言語の多くは対格言語であり、日本語や英語などのなじみ深い言語も対格言語である。能格言語は、バスク語やコーカサス諸語、オーストラリアの原住民の言語、北米インディアンの言語などに見られるが数は少ないという。僻地の言語のイメージである。
能格言語のシステムにピンとこないかもしれないが、対格言語とされる日本語でも能格言語的な表現をすることができるのである。
次の二つの文を見てみよう。
(1) 次郎は太郎が殴る。
(2) 次郎は走る。
(1)で殴る動作を行うのは太郎であり太郎が殴る対象は次郎である。
(2)で走る動作を行うのは次郎である。
動作主を「主語」、被動作主を「目的語」とすれば、(1)での「主語」は「太郎が」と「が」格で表されているのに対し、(1)での「目的語」は「次郎は」と「は」格、(2)での「主語」も「次郎は」とやはり「は」格で表されている。これは、他動詞文での「目的語」と自動詞文での「主語」が同じ格(絶対格)で表される能格言語と同じである。
また、次の文、
(3) 法律は守らなければならない。
(3)においても、「法律」は守るという行為を行う主体ではなく、守る行為を行うのはこの文が置かれた文脈から判る誰かの人である。この文での「法律」は行為の対象となる「目的語」である。
このように、「は」で表す格は「主語」にも「目的語」にもなれるのである。「は」の格がこうした超越的なふるまいをするのは能格言語における「絶対格」的である。
(普通「は」は格助詞とされないが、ここでは格を表すとみなす)
(追記)
他動詞の「目的語」は文の「主題」であることが多い。
「は」は主題を表す助詞である。
上の例のように「は」を用いると日本語でも能格言語的な表現ができるのは、「は」が主題を提示しているからである。
自動詞でも、「主語」が「動作主」の役割を持つ動詞を「非能格動詞」といい、「主語」が「主題」の意味役割を持つものを「非対格動詞」という。
「非能格動詞」とは「走る」「踊る」などのように動作を表すものであり、「非対格動詞」とは、「壊れる」「枯れる」などのように「主語」すなわち「主題」となるものが被る変化を表すものである。
(非能格動詞は主語だけをとる、非対格動詞は目的語だけをとる、他動詞は主語と目的語の両方をとると考える。)
(追記2)
アイヌ語にも能格的な特徴があるという。また自然発生的に生まれた手話にも能格の特徴が見られるともいう。対格システムから能格システムへ変化した言語もあるという。生成文法における普遍文法には対格システムになるか能格システムになるかのパラメーターの違いがあるという説もある。
対格システムから能格システムへ変化するというのは、例えば表現スタイルとして受動態が好んで用いられるようになると、
次郎が太郎によって殴られた。
のような他動詞の受身文での「動作主」を表す指標の「によって」が「能格」として解釈され、こうした他動詞文の「目的語(被動作主)」と自動詞文の「主語」は同じ「が」という「絶対格」でマークされてるいると解釈され、能格言語になっていく、というような変化である。言語習得中の子供にこうした再解釈が起こることで言語が変化していくとされる。
(追記3)
能格システムを持つ言語の中にも、一人称と二人称の関係の時には対格システムで表すなど、能格システムと対格システムが混合して入るケースもあり、事情は複雑である。
主な参項文献